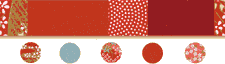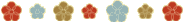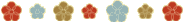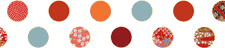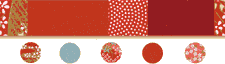
 脳内シグナル
脳内シグナル
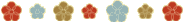
小ネタ【宵桜】
2月21日 07:54
見ず知らずの他人である自分を引き取ってくれた彼は、笑顔が好きだと言っていた。
暖かい色を見せてくれた。
優しい音を聞かせてくれた。
生きるという事を教えてくれた。
なのに自分は何一つ返せなかった。
だから、
ーー「なんつーかさ……折角綺麗な顔してんだから、笑っとけよ」ーー
だからせめて、いつでも笑っていようと心に決めた。
【宵桜】
「さて、どうしたものか……」
人気(ひとけ)の無い林の中、手頃な岩の上に腰を下ろし溜息をつく。辺りを見渡せば酷い有様に思わず引きつった笑みが浮かんだ。
焼け焦げた草木に地面に、恐らく何処かで虫や鼠も焼けてしまったのだろう。においが酷い。
どうやって元に戻したものかと考えて、せめて少しでも水を持って来れば良かったと後悔した
「……はぁ」
再び溜息が漏れる。
とある老夫婦からの依頼を受けて呪詛を祓い、その元である妖を退治したのまではいい。其処までは。
問題は妖が火を操る類のものだったせいですっかり荒れてしまったこの土地だ。何時もの祈祷で済むと思っていた自分が甘かった。暫く家を開ける事になるだろうからと、残してくる少女達が心配で天将達の札はその殆んどを彼方に残してきてしまったのだ。
青龍や白虎が居れば此処まで荒れる前に終わらせられたのに、と。悔やんでも時すでに遅く、自分の未熟さを嘆くばかりである。
「まぁ……大丈夫、だろう」
独特の熱を孕んだ異様な空間で束の間の休憩をとりつつ、彼は小さく言葉を落とした。
『大丈夫』は、宇都美千里の口癖である。
それがいつから染み付いているのかは不明だが、彼は人に頼ると言う事に置いては酷く不器用だった。
今であっても、式神は彼を主と認めているのだ。呼べば飛んできてくれる事だろう。けれどそれが出来ないのはひとえに彼の弱さだった。
パチリと、視界の端で火の粉が爆ぜる。
火は苦手だ。こういう何かの燃える火は特に。嫌でも昔の記憶が自信を苛(さいな)む。
その時差し伸べて貰った彼の手を、何故自分は救う事が出来なかったのか。
炎の渦、崩れる瓦礫、悲鳴、悲鳴、こじ開けられた愛しい檻。思考を止めた愚かな子供。
掌の温度。桜の木。冷たい土。人の心にも鬼が住むのだと、漸く理解できた幼い自分。……嗚呼そうだ、あの時だ。
残された少女達を見た時に、決して弱音は吐かないと。未熟な己を嫌悪して、与えられてきた想いに報いたいと。
だからこそ、自分は笑っていないといけないのだ。
《ご主人ー?》
耳に届いた声に反応して顔を上げれば。黒耀が白天を乗せたまま走ってくるのが目に入った。
大方遅いと探しに来たのだろうが、渦中であったならどうするつもりだったのだ。終わった後で良かったと胸を撫で下ろし、飛びついてくる狼を受け止める。ふわふわとした毛並みが心地いい。
《終わった?》
「……」
《ご主人?》
大丈夫だ、と。胸中で何度も繰り返す。大丈夫。立てる。今度こそ、何があっても新しい家族達を亡くしたりはしない。
《どっか痛いの?》
《まさか怪我をしたんですか!?》
「それはない」
きっぱりと告げて、幼い二人を安心させるようにいつも通りの笑顔を向ける。大丈夫。大丈夫だ。
「後始末がまだ故、暫し待って居てくれるだろうか。取り敢えず火だけでも消さぬと、広がっては事だ」
《はーい》
両手で二匹の頭を撫でてから仕事にかかる。
『務め』を果たす日まであともう少し。曇らぬ様に、折れぬように、逃げぬように。
そして、最後まで笑っていられるように。
******
宵桜の千里さんでした。
今家族って言えるのは孤児の少女が2人と自分が作った式神3体。全員歳下だからしっかりしないと! (・ω・´)キリッってなってる努力家さん
 コメント(0)
コメント(0)
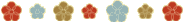
[前へ]
[次へ]
[このブログを購読する]
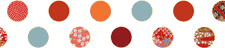
-エムブロ-