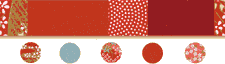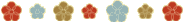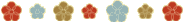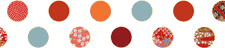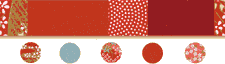
 脳内シグナル
脳内シグナル
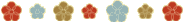
プロラン主従創作
1月20日 13:13
赤い色が嫌いだった。
自身が吐き出す毒々しい色が疎ましくて仕方がなかった。
それを告げた事はないけれど、喀血に毎回険しい顔をする自分を、あの子がいつも不思議そうに自分を見ているのは知っていた。
泣きそうな目をするユウヒとも違う無垢な瞳を、不安そうな静とも違う幼い視線を、何故だか直視出来なかった事を覚えている。
【プロラン主従創作大正パロ(ハクヤ)】
ハクヤの世界はもう随分前からこの寒々しい空間だけだった。
白衣の医者、白い壁、白い天井、白い病衣。最近は日に当たらないせいか自身の肌の色も薄くなってきたような気がして、いよいよ味気ないなとハクヤはこっそりと溜息をついた。それでも変化のない世界は嫌いじゃない。穏やかでいられるならそれでいい。ただでさえ家族に迷惑をかけているのだからと、右腕に固定された針を見ながら眉をしかめる。
ぽたり、と。点滴の中で薬液が落ちた。それがそのまま命の期限のようで目をそらしたくなる。明確な治療法がない今、それはあながち間違いではないかもしれない。
「マスター! 元気?」
「そうだなぁ……今日はだいぶ調子良いよ」
明るい声が部屋に響く。ぴょこんとベッドの脇から顔を出した鮮やかな金髪。病気を移したくなくて見舞客も全て断っているこの部屋に、サポーターだから大丈夫だというトンデモ理論で明るさを運んでくれる少女だ。
毎回ニコニコと笑いながら両手いっぱいのお土産を持ち込んでくる。それは野に咲く花だったり、拾いたてのどんぐりだったり、途中で我慢しきれずに少しだけ齧られたどら焼きだったり、その日によって変わる贈り物は数少ない貴重な変化だった。今日は誰にもらったのか立派な林檎。コロリと布団の上に転がされたそれに、一瞬眩暈を感じて目を閉じる。毒々しい程の赤が怖かった。
「マスター、リンゴは嫌いかにゃ?」
「……嫌いじゃないよ、ありがとう」
「お腹すいてない?」
「うん、でも、折角だから二人で分けようか」
「うさぎさんに切ってほしいにゃ!」
「難しいこと言うなぁ……」
可愛らしいお願いを叶えるために丁寧にナイフを滑らせる。待っている間もどこかそわそわしているメルティが可笑しくて、小さく笑えば少しだけ心が軽くなった。この優しい少女に救われているのだ。それは、もう一人のサポーターにも言えることではあるけれど。
「マスターのお部屋、つまんないにゃー」
「ごめんな、本くらいしかなくて」
「そうじゃなくて、こう、ユウヒが来てる時はもっと楽しかったにゃ」
「ああ……インテリア的な意味か」
容体が悪化して面接が禁止になる前まで毎日通ってきていた元気な妹は、部屋が味気ないと言っては壁を変え、物が少なくて寂しいと言えば柱を変え、頻繁に模様替えしていたなと苦笑いをもらす。どれだけプリズム使ったんだあの子は。今は掃除ができないから片付けて貰っているが何とも賑やかだった事を思い出せば笑うしかない。
愛されている事に負い目を感じる。いついなくなるかも分からない相手にそこまでしなくても。そう言って殴られたのは記憶に新しいからもう二度と口には出さないけれど。
「もっと明るい方がマスターも元気出るにゃ」
「え……まさか、それで毎回お土産くれてたのか?」
「そそ! 白いのばっかりじゃ寂しいにゃ!」
「慣れれば気にならないよ」
「慣れなくて良いにゃ!」
「そう言われてもなぁ……」
苦笑いを浮かべるも、メルティの視線は既に此方を向いていなかった。そのキラキラした先を辿れば窓の外。やんでいたはずの雪が再び静かに舞っている。どうりで静かなはずだと漏らすよりも先に窓ガラスへと張り付いたメルティは、そのまま嬉々として外へと飛び出した。
「メルティ!?」
「マスター、雪!」
「戻っておいで。風邪引くよ」
「サポーターだから大丈夫にゃ」
「その理屈どこまで通るんだ!?」
楽しげに庭の奥へと進んでいくメルティを追いかける為に羽織りを被って外に出れば、冷たい空気が頬を撫でた。小さく身ぶるいをし、思わず首をすぼめたくなる。長い間履いていなかった下駄は少しだけ違和感があったが、そんな事を言っている場合ではなかった。急がねば風邪を引くのはメルティではなく自分かもしれない。
はしゃぐ声を頼りに足を動かせば、一歩進むごとに雪を踏む軽い音がしんと静まる夜に響いた。こうなると腕に繋がったままの点滴が酷く煩わしい。
「メルティ」
「マスター! 見て、見て!」
「……」
木の間からひょこりと覗く金髪。雪の照り返しが反射して一瞬だけ目が眩む。細めた視線の先には相変わらず笑っている少女が真っ赤な花を抱えて立っていた。
「マスター?」
「え、あぁ……それ、椿かな。ダメだよ、手折ったりしたら」
「でも綺麗にゃ。マスターのお部屋に飾るにゃ!」
「……俺の?」
「そしたらマスターのお部屋も、もっと明るくなるにゃ」
「でも、花瓶ないよ?」
「ならマスターに飾るにゃ!」
「どういうこと!?」
任せてくれと意気込むメルティは細い枝をぐにぐにと、ほぼ力技で伸ばして編んで輪っかにしていく。驚いてたのは始めだけ。すぐに何がしたいのか察した後は、ただぼんやりとその様子を眺めていた。
吐き出す息が白い靄に変わる。花はどんどん追加され、隙間なく並べられたそれは見事な冠になっていった。鮮やかな赤が眩しくて、再び優しく目が眩む。けれど、それが花のせいではない事はどうに気付いていた。
「これでマスターも寂しくないにゃ」
自信満々に掲げる椿で編まれた花冠。
赤は嫌いだった。吐き出す血の色を思い起こさせるそれは、嫌いなはずだった。
「そうだな……」
目の奥がじわりと熱を持つ。嫌いなはずの色彩は、メルティの明るい金髪に映えて驚くほど美しく見えた。
「でもな、メルティ。俺は寂しくなかったよ」
少しだけ震えた声を許してほしい。冷たい空気を吸い込んで、そのまま深く息を吐き出す。ぼんやりと霞む視界は優しいけれど、今は君の色を映していたかった。
「メルティ達が居てくれるから……俺はいつも、寂しくなんてなかった」
愛しい君達がいつも鮮やかな世界を運んできてくれた。
それが嬉しくて、暖かくて、いつだって眩しいのは君達だった。この笑顔が好きだった。
「マスター、頭! 頭!」
「ん、ありがとう」
メルティの手が届くように屈めば、頭にそっと乗せられる真っ赤な花冠。同時に感じる椿の匂いと雪の冷たさ。それから彼女の温もりと自身の心臓の脈動。生きている、まだ、今は生きている。
そんな当たり前の事実にまた泣きそうになった事は、きっと誰にも言えないだろう。
******
「信じられません」
「ごめんって」
「メルティはともかく、マスターまで」
「だからごめんって」
翌日、見事に風邪を引いたハクヤは静から呆れたような視線を浴びせられながら苦笑いを浮かべた。その眼からどうしようもなく心配してくれていたのだと分かるから、これはもうひたすら謝るしかない。
「ごめんな。でもさ、楽しかったから。今度は静も行こう?」
「反省してください!」
本格的に怒り出した静を横目にメルティと目を合わせてこっそりと笑い合う。次は3人でお花見がしたいと、交わすゆびきりげんまんを花器に浮かんだ椿が見ている気がした。
★☆★☆★☆
 コメント(0)
コメント(0)
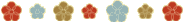
[前へ]
[次へ]
[このブログを購読する]
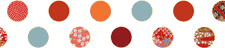
-エムブロ-