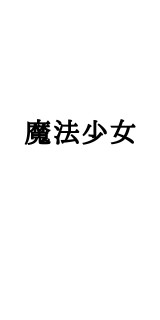剥がれかけのマニキュアを見付ける度に、
ほんのすこし、心がささくれる。
除光液を染み込ませた綿は、薬品の香りを立ち上らせながら淡い桃色に染まる。
スゥッと肌に冷たいその感触は、注射の前のアルコールのそれを思い出させた。
わたしは昔から、この、
マニキュアを落とす作業が好きになれない。
鮮やかな色が吸い取られて消える瞬間の虚しさ。
爪が白くかさつく様子など、ただただ、痛々しい。
そして何より、指がどうしようもなく、ぱさぱさと落ち着かないのだ。
あの水分はどこへ行ってしまったというのか、ぱさぱさと水分を求める指先はどうにも私を脱力させる。
だから私は、
この作業が好きにはなれないのだ。
匂いがダメな訳ではないのにな。
それはまあ確かに、締め切った室内だ、いつまでもこの薬品の匂い居座られるとなると、気も滅入るというものではあるが。
気が滅入るというのは正確じゃないかな。どちらかと言えば、ダメージが与えられるのは精神面よりも肉体面のような気がする。
気化した薬品が鼻から侵入し、狭い管をくぐり抜けて、脳の奥のほうに我が物顔で居座るイメージ。
灯油ストーブも、練炭も、車の排気ガスも、塩素の匂いも好きと胸をはって言える私に、
苦手な匂いがあったなんて。
でもまあ、この匂いと仲良くしたいとは思わないのが正直なところなので、
まあ、いいか。
わたしの爪は、安物のマニキュアしか知らない。
てらてらと光を返すエナメルの感触は、撫でる指の腹にしっとりと馴染んだ。